その1 また高橋洋一先生登場
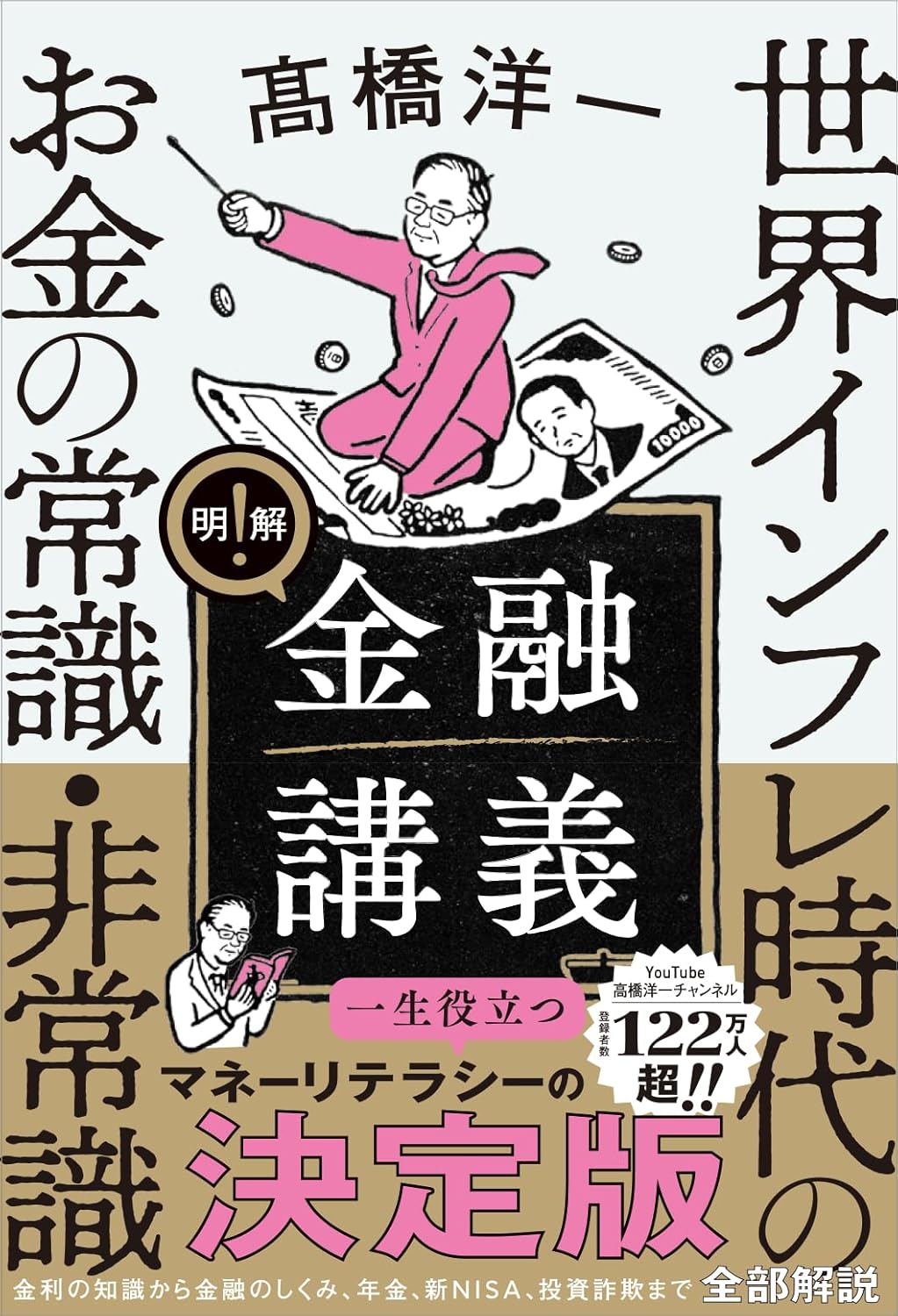
確定申告で忙しかったですね。
でも忙しくなればなるほど本は
読みたくなるものですね。
疲れた身体で深夜ずっと読んでいました。
書評もだいぶたまりましたのでご紹介
していきましょう。
ご存じ高橋洋一さんの本。
何度もこれは書きますが、
「森永卓郎さん亡き後、高橋洋一さんしかいない」
のでしょうね。
「お金」のお話ということですが、
まさに「高橋経済学の基本の整理」ということです。
何度も読み返してみて、経済学の基本を学ぶのには
もってこいの本でしょう。
本当に
「為替とは」
「金利とは」
「金融政策とは」
ということですね。
私もこういうことを大学時代にもっと真面目に
勉強しておけばよかったと後悔しております。
大学でも経済学の講義が確かあったはずでしたが、
たいてい「級友たちと麻雀・・・」
だったからダメなのですね。(反省を込めて・・・)
冒頭「統合政府のバランスシート」から始まります。
これはもう高橋理論の要諦ですからね。
政府のいう「プライマリーバランス問題」の基本のキ。
「量的緩和とは何か」
まあ、このあたり、基本のお話をなぞって
もちろん解説はしません。
「フィリップス曲線」
も前著で出てきましたからね。
でも整理するという意味で、さらにやさしく書かれています。
「金利とは」
「マイナス金利とは」
「利上げ時代の到来」
これからの世の中はどうなるのか。
これを整理するのにはいいのでしょう。
あと、特に「為替の仕組み」これは秀逸です。
「ひろゆき氏に絡まれた事件」
から「そういうことか・・・」妙に納得します。
あとは
「金融からみた戦後日本経済史」
これもいまさらながら驚きます。
誰もこういう解説をしてこなかったのではないでしょうか。
「日本はプラザ合意までは実質的な固定為替相場制」
これも妙に納得してしまいます。
円ドルレートが360円だったら、
あのソニーやホンダが海外で圧倒的に勝てますからね。
「プラザ合意はそういう意味だったのか・・・」
いまさらながら思いますね。
きっと為替に対する認識がまず変わるでしょう・・・。
その2 バブル論の新解釈
バブル経済の真因を見誤った日銀
このあたりの記述が面白い。
高橋先生は「反財務省」だけかと思ったら
「反日銀」でもあるのですね。
日銀の誤りを指摘する方はまたいないでしょうね。
「1985年9月のプラザ合意」
この真の目的と日銀の誤り。
「円高容認」というのはそもそも違うのです。
「日本企業は政府の裏の介入でゲタをはかせ
続けてもらっていたのが、プラザ合意後は
実力で勝負しなければならなくなり、
それまでのような儲け方は不可能になった」
そのあとも日銀は見誤ったというのです。
「失われた20年」
はあたかも日銀のせいであるという指摘。
「各国が金融緩和をさかんに進めているにも
かかわらず金融引き締めに走った」
ではあのバブルというのは何だったのか?
[1987年から90年までの実質成長率は
4.2%から6.2%でそれほど高いわけではない」
それでも「異常に高騰していたのは株価と不動産価格」
では誰が犯人か?
「バブル経済を導いた証券会社と民間金融機関」
厳しいですね。
ここで懺悔を込めて申し上げます。
時代の生き証人として。
「犯人は証券会社です。犯人は私です・・・」
その3 日銀のミスとミスを認めない日銀
バブル時のお話は懐かしく読みました。
「資産価格はマネーがあふれていなくても、
回転率の高さで上昇することがある。」
「資産価値が上昇すると担保価値増加して
資金調達や融資を受けられる余地が拡大するため
その資金の一部が再び資産市場に投入されて
資産価格はさらに上昇するというスパイラルが
発生する」
「1980年代日本のバブルは、
まさに証券会社と銀行によって引き起こされた」
このバブルの原因を日銀は見誤ったというのです。
「公定歩合は1980年8月に9.0%から
8.25%に引き下げて以来、1987年2月の
3.00%から2.50%へ引き下げまで
10回引き下げた。」
すごいですね。
いまさらながら9.0%から2.50%へ。
その後1990年8月までに
公定歩合が4回も引き上げられ6.0%へ。
こんな「ジェットコースター」みたいな金融政策を
当時の日銀はやったのですね。
結果どうなったのか?
私ももう少し経済学を勉強しておくべきでしたね。
あの頃高橋先生から学びたかった・・・。
「バブル崩壊は誰の目にも明らかだった」
「4回の利上げはまったく不要だった」
これ何だか今の情勢を予感していませんか・・・。
「利上げのタイミングが遅れると、その後の引き下げは
完全に後手に回り、景気回復ができなくなる。
ここからまさに悲劇というべき『失われた20年』が
始まるのである」
手厳しいのですが、その後の日銀のせいで
「失われた20年」
が起きたというのです。
バブル当時盛んに「カネ余り」だといわれましたね。
高橋経済学を学べば、
「カネ余り=通貨供給量が多すぎるなら
物価は上がるはず。」しかし一般物価は安定していた」
ということは
「当時取った金融引き締め策は間違いであった」
と高橋先生はいうのですね。
でも
「日銀の官僚たちは金融引き締めが間違いだったとは
決して認めない」
のですね。
しかも
「過去の間違いを正当化するために、その後もずっと
誤ったタイミングで引き締めを続け、デフレを引き起こし、
放置し、悪化させた。犠牲となったのは一般の日本人である」
なかなか天下の日銀に対してこれだけ真正面から
批判できるのは高橋先生だけでしょうね・・・。
その4 このお方が犯人?
(高橋先生ご指摘のバブルの犯人)
「失われた20年」の原因。
これは勉強になりました。
こういう論点で経済をみるのかと。
そもそもバブルはなぜ起こったのか?
その原因を見誤ったかたと。
一般物価は問題のない水準だったのに
金融引き締めに走ってしまったと。
それを間違いだと認めなかったから
失われた20年の泥沼にはまってしまったと。
資産価格のバブルはなぜ起こったのか?
まさに証券会社と銀行のせいだったと・・・。
これ本当に「時代の生き証人」としていまさらながら
しみじみ思うのですね。
当時某野村證券の某子会社の企画で
「資産効果の有効利用」
というのがテーマでした。
「バブルで膨らんだ資産価値をどうやって
うまく活用するか?」
この資産価値を最大限利用するには
その担保価値にさらなら貸付を
実行し別の資産を買わせる・・・。
それが株式であれ不動産であれ・・・。
また証券会社本体でも時価発行増資で
調達した「タダ」の企業の資金を
「元本保証」で運用した・・・。
株価を釣り上げて、時価発行増資で
さらなる資金調達をして・・・。
まさにそれの繰り返し。
それをこの本に書いてあるように
「証券会社の営業姿勢の適正化及び
証券事故の未然防止について」
という通達を1989年12月26日
に出していたのですね。
このお話は当時現役の証券マンとしては
まさに「初耳」・・・。
その3日後の大納会で日経平均が
最高値を付けたのですからね。
当時は中で働いた証券マンは
「このまま10万円までいくと信じて
疑わなかったのですから・・・」
その後バブル崩壊で「元本保証」は
大変な問題になりますね。
野村證券は「営業特金」で多額の運用を
していましたから。
1991年6月27日の
野村證券の株主総会。
当時の野村證券社長であった田淵義久氏は
「大蔵省にご承認いただき、損失補填した・・・」
大問題になりました。
これこのブログで何度も書きましたが、
最前列で「社員株主」として一番前に座っていた
私は、「全世界の誰よりも近い場所」で
聞いておりました。
大損した怒りに狂った一般株主から
「身を挺してでも」営業の神様を
守る役割だったのですね・・・。
(今だから言えるお話)
その5 賃金が上がらない日本
まあ、「得意の」昔話はこれくらいでいいでしょう。
その後の「失われた20年」とその後の「アベノミクス」
までよく読んでください。
高橋先生の言う通りの展開になっています。
さすが真の経済学者ですね。
こういう基本を勉強するには非常に良い本です。
アベノミクスの効果が出なかったのは
「2度にわたる消費増税とコロナ禍」
なんだか恨み節のようです。
日銀の役割というのもなかなか勉強になります。
はたして今後はどうなるのか。
まず日本はそれほど賃金は上昇していません。
最近上場企業で「初任給が30万円・・・」
なんて報道されていますが、
中小企業ではとんでもないことです。
まず世界の国々ではだいたい10年くらいで
賃金が2倍くらい上がっていますね。
日本だけ上がっていません。
その証拠として初めてアップするネタですが
今から30年前の1994年に、税理士試験を
受けながら駐車場で警備員のバイトしたおとがあります。
(詳細はブログで)こちら。
あの頃の時給は1200円。
今よりいいくらいでしょう。
平均賃金の推移を
よくよく見て考えてください。
高橋先生は、
「誤った金融政策で『人災』以外何物でもない」
と手厳しい。
これは理解できるでしょうけど
「経済が伸びなければ賃金も伸びない」
当たり前のことです。
これも経済用語の基礎。
実質賃金とは、労働者が実際に受け取った給与(名目賃金)
から物価上昇分を除いたもの。
当然実質的な購買力を表すもの。
でも現状ではどうでしょう。
「名目賃金がインフレ率を追い越さなければ
実質賃金は上がらない」
それが今の日本の現状だからです。
その6 やはりフィリップス曲線
経済学の基本で、この高橋先生お得意の
「フィリップ曲線」
前にご紹介した本にも掲載されていましたし、
この本ではなんと!2度も出てきます。
よくよく見て考えてください。
「日銀と金融機関が金利を上げようとしている」
まさにこの局面で日本はいったいどうなるのでしょうか?
今日本はどこの局面かこれを見誤ると
過去のような失われた20年が30年、40年と
続いてしまうのですね。
インフレ目標2%のラインが分かりますか?
インフレ目標が2%を超えても4%程度まで
我慢したほうがいいのです。
そこで初めて
緊縮財政、つまり金融引き締めを
すべきところなのです。
いまはまだまだ左側の局面です。
大事なところは増税可能なラインも
ずっと右側だというのです。
「増税も避けられない」
という政府の主張は間違っているし、
「プライマリーバランスを持ち出して
増税を正当化することもおかしい」
のです。
ここで難しい図が出ていました。
潜在GDPとGDPの推移。
まだGDPギャップが10兆円もあるというのです。
このまま拡大すると失業率は上がり、
デフレに逆戻りする可能性があるというのです。
日本が金利を1%上げると1〜3年後には
GDPが0.2%低下、インフレ率も0.1%低下すると
いうのです。
つまり日本はまだまだ金融緩和すべき局面だというのです。
どうでしょう。
経済学の基本を学べば分かりやすいと
思うのです。
なかなか勉強になると思いませんか。
これからも高橋経済学を勉強しようと思います。
ありがとうございました。